認知バイアスを理解して、より良い意思決定をしよう!

人の頭はバイアスだらけです。
私は特にそうかもしれません。
例えば、仕事で出会う方が、スタイルが良く、高そうなスーツをさりげなく着こなし、最先端のガジェット類を持って打合せに来たら、この人は仕事が出来そう!というイメージを持ちます。
実際にはまだ一緒に仕事をしていないのに、見た目だけで仕事が出来るであろうと判断しているこの認知バイアスは少し危険かな!?と感じています。
このように、人が普段かかっている認知バイアスは、自分や人(他人)がどのようなバイアスにかかり易いかを理解することで、バイアスへの対策を講じたり、逆にバイアスを利用したり出来ると思います。
このページでは、認知バイアスの基礎情報と、その対策や活用方法について書いています。
バイアスとは何か!?


そもそも、バイアスとは
バイアスとは、偏りや偏見、先入観を意味し、認識の歪みや思考の偏りを表す言葉として使われます。

認知バイアスって何?
- 人が情報を認識・判断する際に、先入観や感情、常識や固定概念などに影響されて、合理的ではない判断をしてしまうこと
- 様々な理由で認識が歪んでしまい、事実を正しく認識できずに不合理な(事実でない)認知をしてしまう傾向
認知バイアスは非常に多岐にわたり、研究者によって100以上のタイプが識別されているようですが、ここでは、よく見聞きする代表的な認知バイアスの事例「ベスト10」を簡略的にご案内します。

認知バイアスの種類は?
代表的な認知バイアス「ベスト10」
①確証バイアス
自分の考えや仮説を支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視・軽視する傾向のこと
②正常性バイアス
災害や危険な状況が発生しても、それが自分には関係ない、大丈夫だと過小評価してしまう傾向のこと
③ハロー効果
ある対象の目立つ特徴に引きずられて、他の特徴に対する評価
もゆがんでしまう現象のこと。
➃フレーミング効果
同じ情報でも、表現の仕方や伝え方によって、受け手の判断や選択が変わってしまう現象のこと
⑤アンカリング効果
最初に出された情報(アンカー)に引きずられて、その後の判断が偏ってしまう現象のこと
⑥バンドワゴン効果
周囲の人々が支持しているものに、自分も支持したくなる現象のこと。
⑦自己奉仕バイアス
成功は自分の能力のおかげ、失敗は他人のせいにする傾向のこと
⑧現状維持バイアス
変化を嫌い、現状を維持しようとする傾向のこと
⑨アンコンシャス・バイアス
無意識の思い込みや偏見のこと。
過去の経験や知識、周囲の意見などから、無意識のうちに偏った考え方を持つこと
⑩感情バイアス
意思決定や判断が「感情」によってプラスマイナスの影響を受ける認知バイアスのこと
私のバイアス、ベスト3

1.アンコンシャス・バイアス
冒頭に書いた、私が人を見た目で判断してしまうバイアスは、アンコンシャス・バイアスであり、自分のこれまでの経験や、見聞きしてきた情報を基に、無意識のうちに人を見た目で判断しているのだと思います。
2.確証バイアス
仕事で会議資料を作成している時や、情報や戦略の分析をしている時に、自分にとって都合の良い情報を拾ってしまう。これも確証バイアスです。
私は、これもよくやってしまうのですが、もはや無意識ではなく意図的に取りに行ってる感じです。反省、、、
3.感情バイアス
人は感情の生き物だと言われますが、私は特にその傾向が強いかもしれません、ここは自覚しているので、目標管理(MBO)などの評価時には、自分の好き・嫌いが評価に影響しないように、メチャメチャ気をつけています。
事実よりも、好き嫌いなどの感情で動いてしまう。これは立派な感情バイアスです。
認知バイアスを利用する
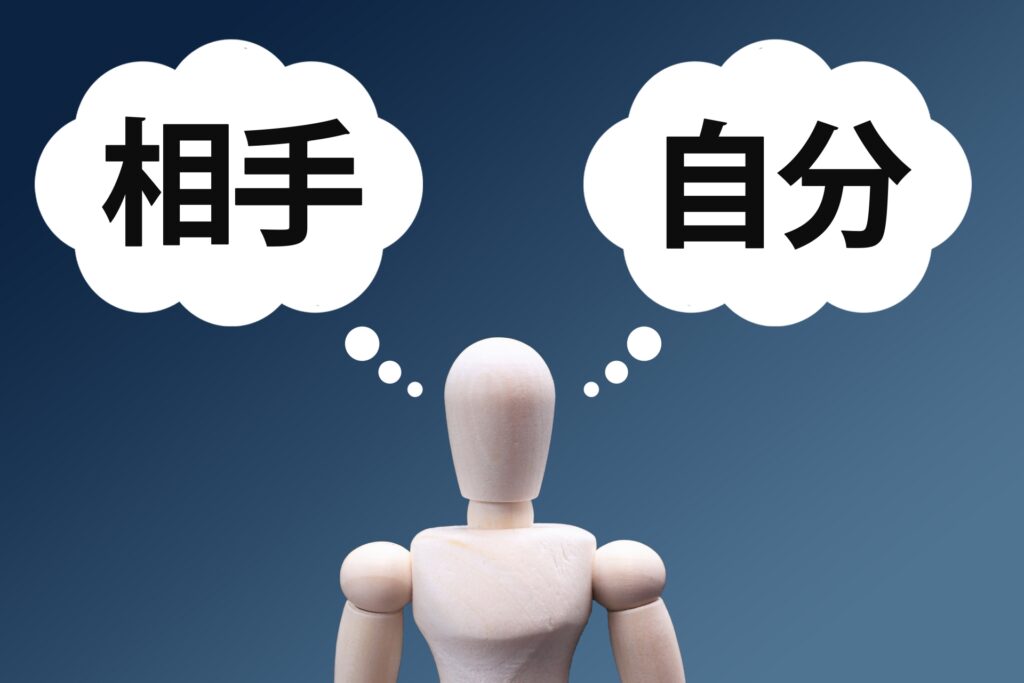
認知バイアスをうまく利用する方法は、状況や目的によって様々ですが、大きく分けて「自分自身の認知バイアスを理解し、その影響を軽減する」ことと、「他者の認知バイアスを理解し、それを利用する」ことの2つの側面があります。
1.自分自身の認知バイアスを理解し、その影響を軽減する
私たちは皆、無意識のうちに様々な認知バイアスの影響を受けています。これらを理解し、軽減することで、より合理的で良い意思決定ができるようになります。
先ず、どのような認知バイアスが存在するかを知り、自分がどのような状況でどのバイアスにかかりやすいかを自覚することが第一歩です。
例えば、私の確証バイアスの場合は、 確証バイアスにかかり易いと自覚していれば、意識的に反対意見や異なる視点を探すようにします。
そのためにも、自分がかかり易いバイアスを知り、バイアスへの対策を講じて行きましょう。
以下の2点は、どのバイアスにも効果的な対応策になると思います。
ご参考までに。
①他者からのフィードバックの活用
信頼できる友人、同僚、メンターなどに意見を求め、自分の思考の盲点やバイアスを指摘してもらう。特に、自分とは異なる意見を持つ人からのフィードバックは貴重です。
②チェックリストやフレームワークの活用
特定の意思決定プロセスにおいて、バイアスを軽減するためのチェックリストや意思決定フレームワーク(例:SWOT分析、意思決定マトリックスなど)を活用することで、網羅的に情報を検討し、客観性を保つことができます。
2.他者の認知バイアスを理解し、それを利用する
他者の認知バイアスを理解することは、コミュニケーション、交渉、マーケティング、リーダーシップなど、様々な場面で役立ちます。ただし、悪用は避け、倫理的に利用することが重要です。
アンカリングの効果は、私たちの日常生活でよく見聞きするバイアスとして、分かり易いと思いますが、こういうバイアスがあると知っておくことや意識しておくことが大切だと思います。
■よく目にするアンカリング効果
通常価格を高く設定することで、割引後の価格をより魅力的に見せる。例えば、10,000円の商品を「通常価格15,000円、特別価格10,000円」と表示すると、10,000円が安く感じられる。
仕事でもプライベートでも、色々なバイアスを理解し、適切に活用することで、より効果的なコミュニケーション、説得、意思決定が可能になると思います。
しかし、最も重要なのは、それらの知識を倫理的に、そして他者を尊重する形で利用することです。
まとめ
学生時代に、親や学校の先生からは、人は見た目によらないよ!と言われて来たのに、今でも人を見た目で判断している自分がいます。
なので、先ずは自分が持っているバイアスを知り、バイアスがかかっていることに気がつけるようになることで、その対策を講じて行きます。
自分のバイアスに素早く気がついたり、バイアスを理解した上で、バイアスを上手に使える習慣を身につけたいですね。
このページが、少しでも読んで頂いた方の参考になれば幸いです。
参考資料
以下へ、バイアスを分かり易く解説しているサイトを記載しておきます。
ご参考までに。
以上






