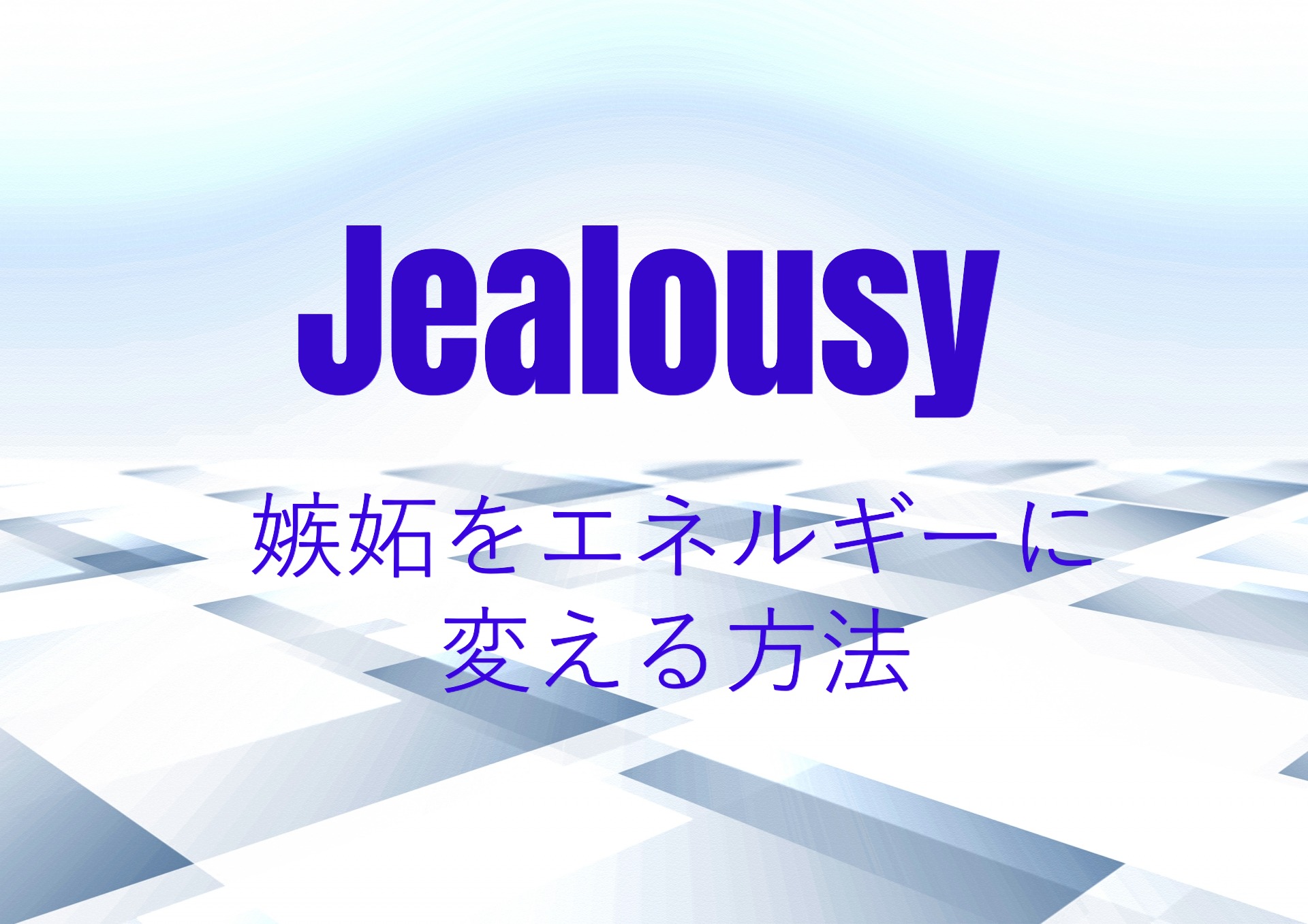同じ会社でも別世界

2025年4月から、約20年務めた営業職から、事業戦略を担う管理部門へ異動になり、これまでと異なる職務や部署のやり方に、ワクワクしたり、戸惑ったりしながら2か月半が経ちましたが、部門が変わると同じ会社でも雰囲気が全然違うし、独自のルールがあったりするし、組織って本当に面白いな!と感じています。

このページでは、部門を跨いだ人事異動を経験して感じた、ジョブローテーションについての感想を書いています。
ジョブローテーションを経験して思うこと

ジョブローテーションにより新しい部署へ配属されてから、まだ2か月半ですが、現時点ではジョブローテーションは必要だと思うし、上手くいくと社員にも会社にもメリットがあると感じています。
その理由は、
同じ社内の仕事でも、これまで関わることのなかった業務に携わると、見えていなかった大変さや苦労が分かるし、逆に、想像よりも簡単だったり楽な面も分かります。
それに、これまで関わったことのない人達と一緒に仕事をする楽しさや、人間関係をつくる苦労、信頼関係を築く難しさも経験できます。
仕事の進め方を学び直したり、新しい人間関係をつくり直したり、同じ社内にいながら、転職したような、エキサイティングで新鮮な経験もできます。
苦労やストレスが無いとは言いません。むしろ、新しい環境に身を置く社員にとっては、様々な面で苦労も多いと思います。
私自身も、大変だと感じることが多々あります。
しかし、それを踏まえても、新しいチャレンジをし、環境の変化に対応することは、自分も会社も成長するチャンスだし、ポジティブな面は多いと感じています。
ジョブローテーションを行う意味


そもそも、なぜ企業(会社)はジョブローテーションを行うのか?
企業がジョブローテーションを行う主な理由は以下の通りです。
- 人材育成: 複数の部署や職種を経験させることで、幅広い知識やスキルを身につけさせ、将来の幹部候補や多岐にわたる業務に対応できる人材(ジェネラリスト)を育成する。
- 適材適所の見極め: 社員の適性を見極めたり、新たな可能性を発見したりすることで、最適な人員配置の実現を目指す。
- 組織の活性化・属人化防止: 部署間の交流を促し、情報共有を活発にすることで、組織全体の連携を強化し、特定の個人に業務が集中する属人化を防ぐ。
- 変化への対応力強化: 社員が様々な環境に適応する経験を積むことで、企業の環境変化への対応力を高める。
以上のように、企業は「組織」と「個人(社員)」の、成長と最適化を目指してジョブローテーションを行っています。
だから、もし自分にジョブローテーションの話が来たら前向きに捉えてください。
ジョブローテーションによる好機

ジョブローテーションは、社員の仕事の幅を広げるだけでなく、他部門とのコミュニケーションの活性化や、部門独自の組織文化に新しい風を入れる役割もあると思います。
私は、組織も個人も、変化に対応しながら成長して行く必要があると考えています。そのため、ジョブローテーションは変化を受け入れ、変化を楽しみながら成長するチャンスだと思っています。
ここまで書いてきたように、新しい部署で働くことには沢山の苦労もあります。しかし、それを踏まえても、自分と会社が変化に挑戦し、成長を目指すジョブローテーションは、やりがいのあるチャレンジだと考えています。
実際にジョブローテーションを経験してみて思うことは、新たな職務の中で、新しい発見をしたり、新しい目標を見つけたりする良いきっかけになっていると感じています。
ジョブローテーションは、同じ会社にいながら、これまで関わることのなかった人や、これまで経験したことのない業務を行える為、新鮮な経験を味わえるし、新しい仕事を覚えて成長する良い機会になります。
転職のように会社を変えるリスクを取らずに、新たな経験ができるジョブローテーションは、会社にとっても社員にとっても、成長するチャンスだと思います。
まとめ
比較的早く変化を受け入れ、新しい環境を楽しめる人もいれば、変化を受け入れるまでに時間が掛かる人もいると思いますが、ジョブローテーションによる変化は、ポジティブに捉えて良いと思います。
ジョブローテーションを経験するタイミングは、人それぞれ様々だと思いますが、その機会を前向きに捉えて欲しい、そんな思いでこのページを書きました。
このページが、少しでも読んで頂いた方の参考になれば幸いです。